『左右盲(さゆうもう)』は、病気や障害ではなく、とっさに右と左の判断ができない状態を指す俗語です。学術的には左右識別困難、左右失認、左右誤認とも呼ばれます。左右盲の人は、左右を判断する際に数秒の思考を挟む必要があり、例えば「右は鉛筆を持つ方だから…」といったように、何らかの基準を頭の中で参照することが多いです。
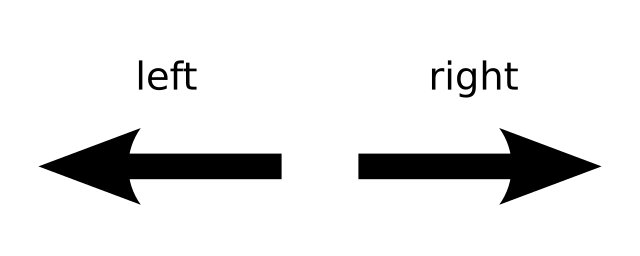
具体的な状態
具体的には以下のようなあるあるが挙げられます。
- 咄嗟の指示(「右手をあげる」「左を向け」など)に反応できない
- 視力検査でランドルト環の向きを言葉で答えるのが難しい(指で示す、レバーで操作する方が楽)
- 車の運転中にカーナビや同乗者の「右折」「左折」の指示で間違って曲がってしまう
- 「右回り」「左回り」といった言葉で混乱し、「時計回り」「反時計回り」と変換する必要がある
- 対面している人の左右や、鏡の中の自分の左右を混乱する
- 考えるのが面倒で当てずっぽうで答えてしまい、間違えることが多い
- 「上下と同じ感覚で左右がわかる」という人がいることに驚く
- インストラクターなどが左右反転して動きを教える際に混乱しないか心配になる
割合と特徴
左右盲の人は意外と多く、人口の15%から25%程度、つまり約4人に1人が左右盲であると言われています。男性よりも女性に多い傾向があるとされていますが、その原因はまだ解明されていません。
左右盲は遺伝するものではなく、発達過程で生じるものと考えられています。特に左右盲になりやすい人の特徴として、以下の3点が挙げられます。
- 過去に左利きを矯正した人
生まれつきの利き手と異なる手を使うように矯正されたことで、左右の 感覚が混乱しやすくなると考えられています。本来の利き手の感覚を意識することで改善する可能性も指摘されています。 - 視覚優位の人
言語情報よりも視覚情報で物事を処理しやすい人は、左右の言葉と言葉が指し示す方 向を結びつけるのに時間がかかる傾向があるため、左右盲になりやすい可能性があります。
対処法
左右盲は医学的な定義がない俗称ですが、多くの人が抱える共通の悩みです。左右盲は日常生活で不便を感じることが多く、特に車の運転中や集団行動の指示などで他人に迷惑をかけてしまうことにストレスを感じる人もいます。しかし、多くの人が経験する一般的な特性であり、過度に気負う必要はありません。
左右盲の根本的な治し方は確立されていませんが、ストレスを減らし、日常生活を快適にするための対処法がいくつか提案されています。
- 体の特徴を利用する
左右を瞬時に判断できるよう、利き手や、ほくろ、腕時計、指輪など、決まった手にある特徴を判断基準として意識的に利用する方法が有効です。これにより、考える時間を短縮し、間違いを減らすことができます - 周囲へのカミングアウト
左右盲であることを周囲の人に伝えることで、理解を得られ、指示の出し 方を変えてもらうなど、小さなトラブルや無駄なストレスを回避できる場合があります
病気との関係
左右盲はそれ自体が病気や障害ではありません。しかし、発達障害やゲルストマン症候群などの病気によって左右盲の症状が現れる場合もあります。左右盲の症状だけでなく、文字が書けない、計算ができない、指が上手に動かせないといった他の症状が併発している場合は、脳の損傷の可能性もあるため、医療機関を受診することが推奨されます。
左右盲と学力(頭の良さ)には直接的な関係はないとされています。また、左右盲であることと方向音痴であることも直接的な関係はありません。左右盲の人は地図上の左右の識別は苦手でも、実際に通った道であれば迷わないなど、方向感覚自体は持っている場合が多いです。